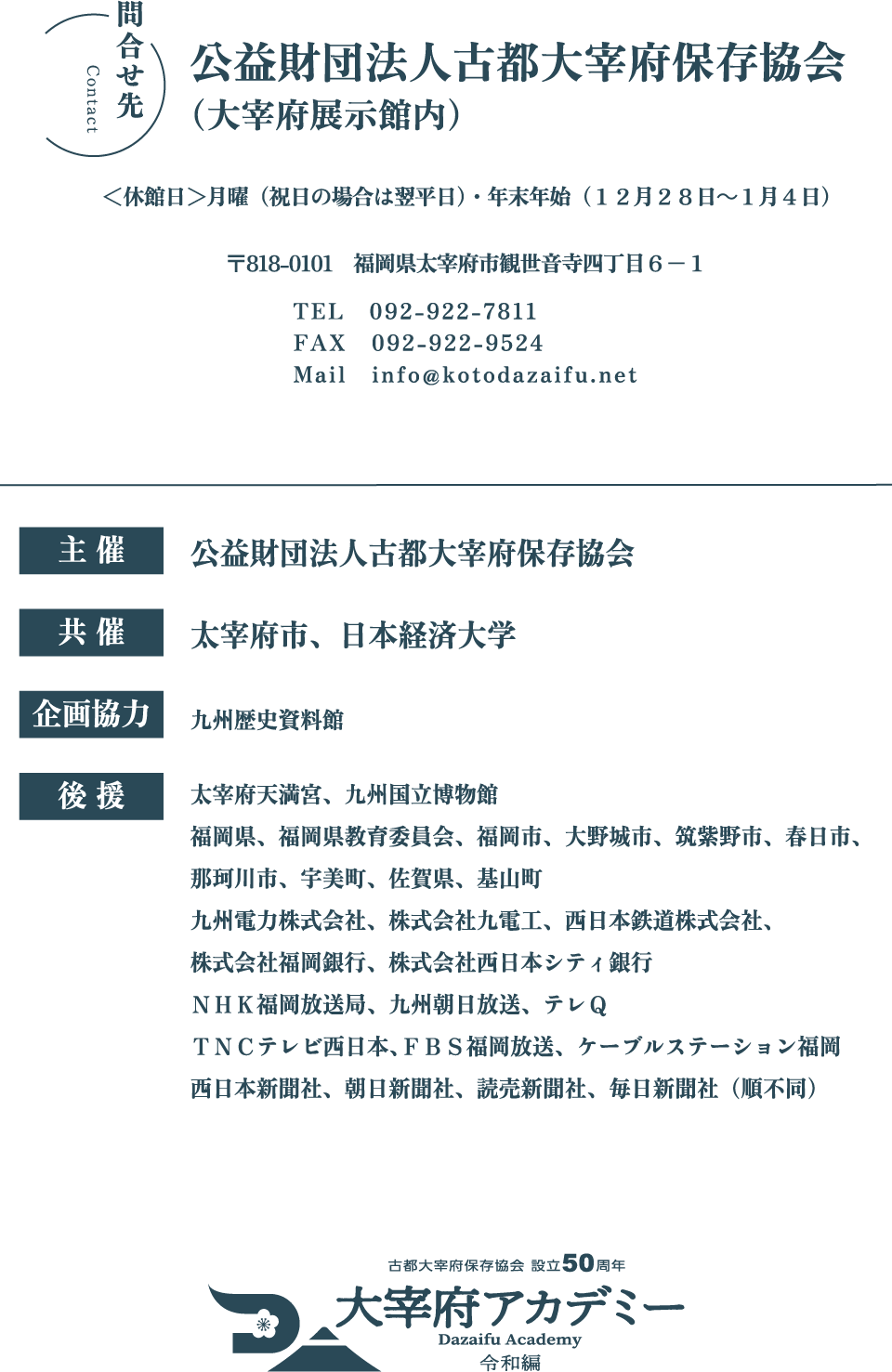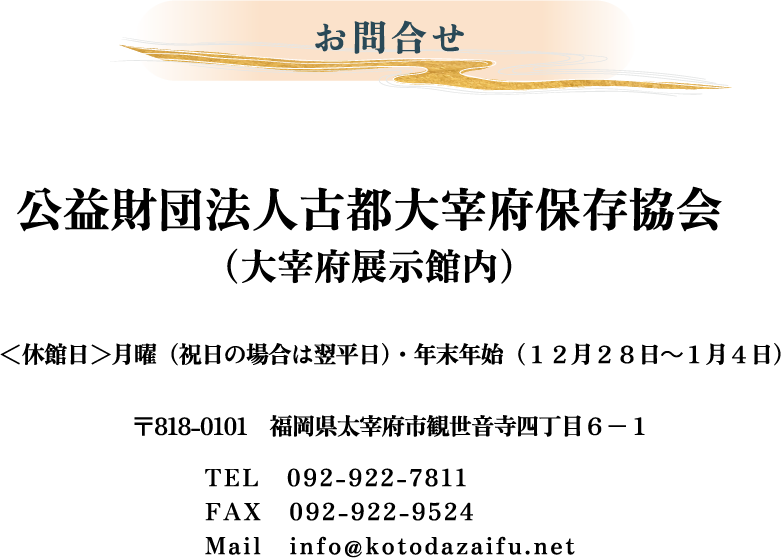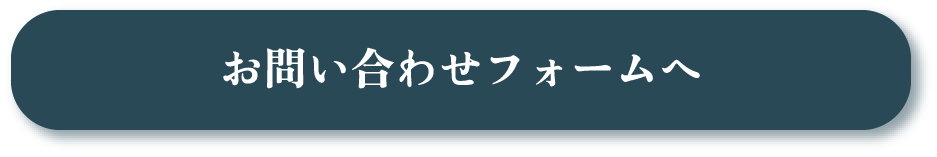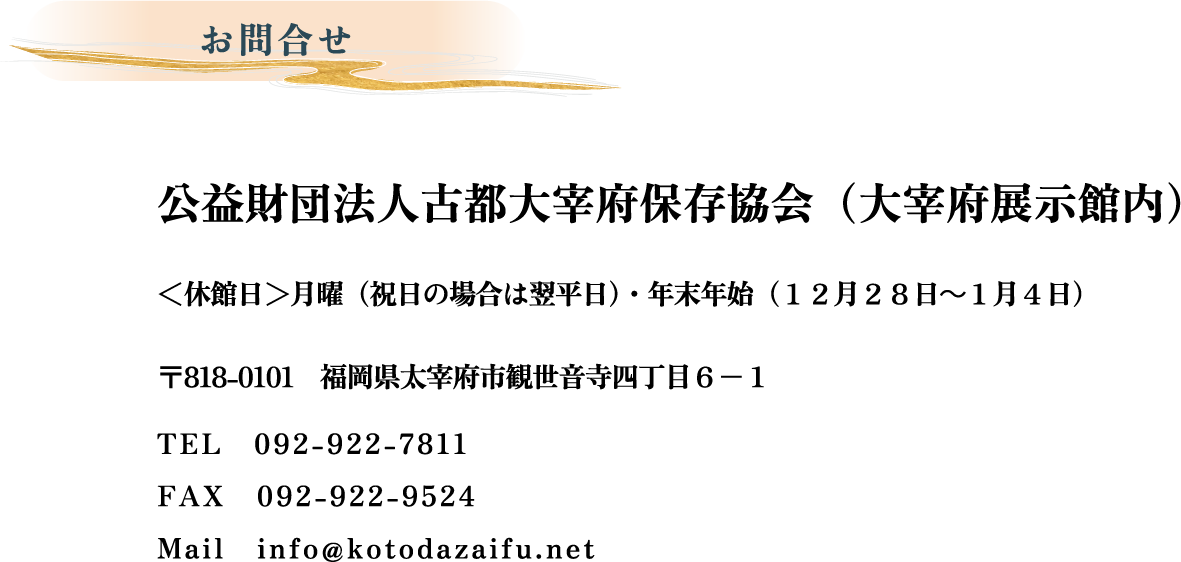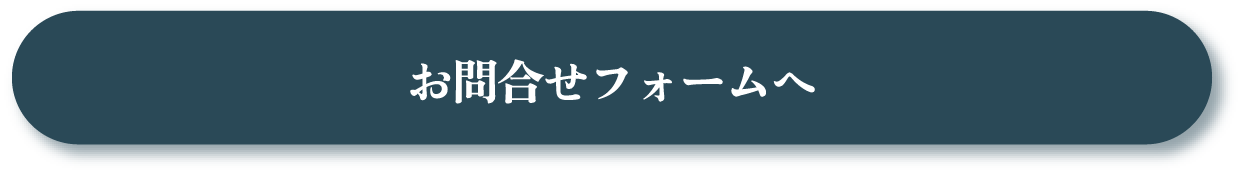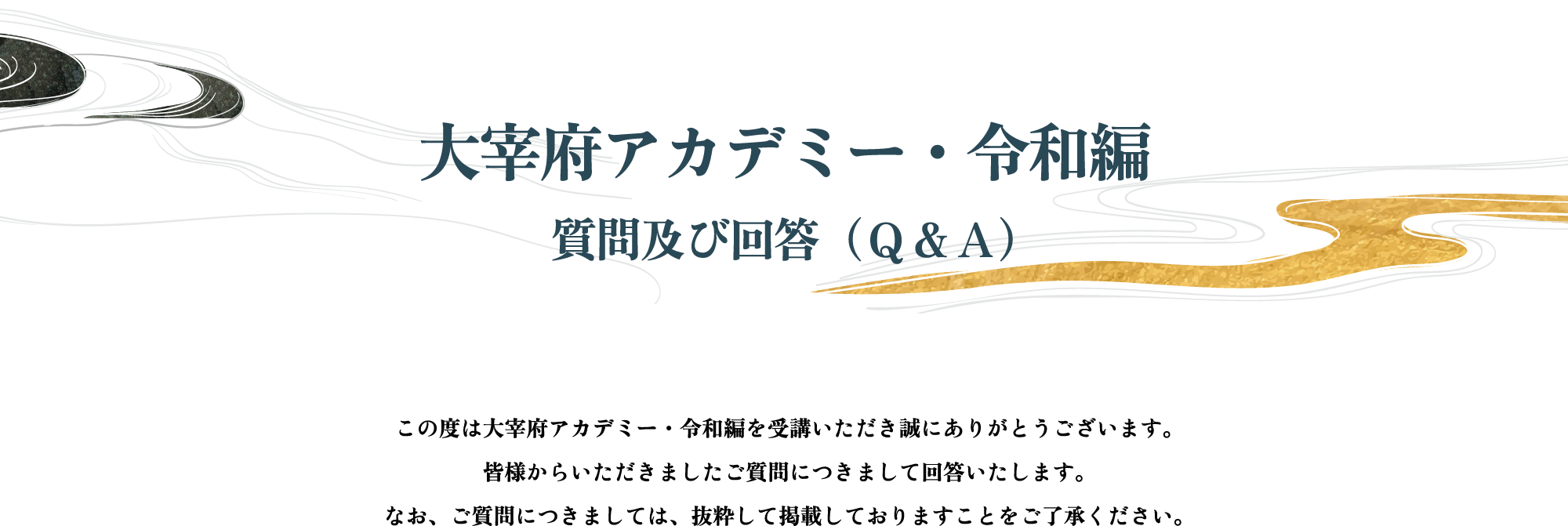
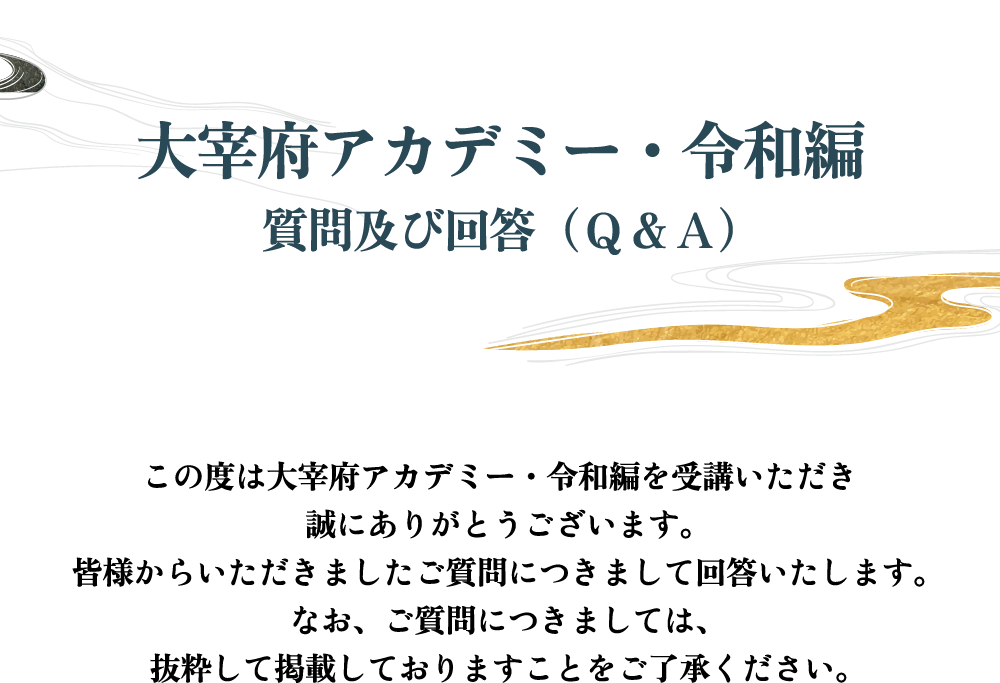
◎第15講 令和6年6月19日(水)
「鎌倉時代の大宰府~少弐氏と蒙古襲来~」
講師・回答:服部英雄先生(九州大学名誉教授)
講師・回答:服部英雄先生(九州大学名誉教授)
先生が講座の最後にお話しをされていた「神風」に関連して質問します。「弘安の役」の際、竹崎季長が参戦した博多湾の戦場ではとりたてて荒天ではなかった(だから絵詞には描かれていない)、しかし鷹島では暴風が吹き、多くの船が沈んだ、という理解でよいのでしょうか?
台風については、京都の記録に「自上古第三度」と書かれており、超大型台風でしたから、日本全土に大きな被害を与えたと考えています。講座でも「荒天ではなかった」とは申し上げなかったし、蒙古船が多数沈んで戦局に大きな影響を与えたこと、また蒙古軍が引き上げる要因になったことまで否定するものではありません。
ただし台風通過は閏七月一日、生の松原・博多湾海戦は閏七月五日で、絵詞を見る限り蒙古船団は健在です。また、鷹島海戦は閏七月七日ですから、やはり閏七月一日に壊滅してはいません。さらに日本側の船が不足していたことは、季長が乗る予定の(安達盛宗)兵船Aの遅延、沖合にいた安達の大型兵船Bが季長一行わずか五人ほどの乗船を拒否したこと(過積載・定員オーバーのため)から推測できます。つまり日本側の船も台風被害に遭っていたのです。季長は、大風のおかげで勝ったとは考えず、自分たちが戦って相手を倒したと考えていましたから、絵詞を作成したのです。
ただし台風通過は閏七月一日、生の松原・博多湾海戦は閏七月五日で、絵詞を見る限り蒙古船団は健在です。また、鷹島海戦は閏七月七日ですから、やはり閏七月一日に壊滅してはいません。さらに日本側の船が不足していたことは、季長が乗る予定の(安達盛宗)兵船Aの遅延、沖合にいた安達の大型兵船Bが季長一行わずか五人ほどの乗船を拒否したこと(過積載・定員オーバーのため)から推測できます。つまり日本側の船も台風被害に遭っていたのです。季長は、大風のおかげで勝ったとは考えず、自分たちが戦って相手を倒したと考えていましたから、絵詞を作成したのです。




「蒙古襲来絵詞」の絵師は誰だったのでしょうか?竹崎季長がいわば「戦場カメラマン」的に連れていった配下の絵師だったのでしょうか?絵師自身が戦場にいたということでしょうか?
絵詞を描いた絵師は、少弐景資の馬具足を見て似絵を描いていますから、大宰府にいたと考えます。大宰府には画工司があって、大宰府が「戦場カメラマン」=従軍絵師を派遣したと推測します。彼らは多くの戦場スケッチを画工司に残していました。本来なら大宰府画工司が本業として合戦絵巻を作成したはずで、その準備中であったか、またはすでに作成していたかもしれません。竹崎季長は、その大宰府絵師に絵詞作成を依頼したと推定しています。




■Q&A 印刷用PDFデータ(268.43KB)
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。◎第14講 令和6年5月15日(水)
「少弐氏・大内氏の抗争と大宰府」
講師・回答:佐伯 弘次先生(九州大学名誉教授)
講師・回答:佐伯 弘次先生(九州大学名誉教授)
「応永の外寇」では、対馬が朝鮮から攻められていますが、対馬には本当に「倭寇」の本拠地があったのでしょうか。また、宗氏と倭寇との関係はどうだったのでしょうか。
倭寇に関しては『高麗史』、『朝鮮王朝実録』、『元史』等の海外史料が主要なもので、日本国内の史料が少なく、実態の究明が難しいという特徴があります。『朝鮮王朝実録』には、「三島の倭寇」「三島の倭人」という表現があり、この「三島」とは、対馬・壱岐・松浦地方という考えが有力です。実際に、応永の外寇の直接のきっかけとなった1419年の倭寇は対馬の島民であると『朝鮮王朝実録』に出てきます。
対馬島主・宗氏は、宗貞茂の代から倭寇の沈静化に努力しました。それは宗氏が倭寇を押さえることによって、朝鮮との通交を有利にするためとされています。
対馬島主・宗氏は、宗貞茂の代から倭寇の沈静化に努力しました。それは宗氏が倭寇を押さえることによって、朝鮮との通交を有利にするためとされています。



講座のなかで、少弐・宗体制の崩壊を述べられていましたが、その理由・背景にはどのようなことがあったのでしょうか。
「少弐・宗体制」という言葉を作ったのは私です。これは、室町幕府における「細川・三好体制」という概念があって、それにヒントを得た表現です。室町時代、大宰府を追われた後、少弐氏は主として対馬に居住することになり、旧家臣である宗氏の庇護を受けました。宗氏は少弐氏の朝鮮通交も援助しました。少弐氏が対馬から筑前に進出する時も、常に宗氏の軍事的支援があり、一時的に筑前ー太宰府を回復することもありました。少弐氏は旧地・大宰府を目指し、宗氏は貿易の中心地・博多を目指します。両者の利害が一致したため、こうした連合が成立したものと考えています。
しかし、講演でも述べたように、応仁の乱時に少弐氏が筑前を回復した時、千葉氏救援問題で少弐頼忠(政資)と宗貞国が不仲となり、貞国が帰島しました。少弐氏は文明10年(1478)に肥前に逃れ、九州に残っていた宗氏の家臣団は対馬に帰ります。こうした流れと並行して、大内氏の工作によって、室町幕府から、少弐氏に味方すべからずという命令が宗貞国に届きます。貞国はこれに従いました。つまり、少弐氏と宗氏の関係悪化と大内氏の政治的工作によって少弐・宗体制は崩壊したと私は考えています。
しかし、講演でも述べたように、応仁の乱時に少弐氏が筑前を回復した時、千葉氏救援問題で少弐頼忠(政資)と宗貞国が不仲となり、貞国が帰島しました。少弐氏は文明10年(1478)に肥前に逃れ、九州に残っていた宗氏の家臣団は対馬に帰ります。こうした流れと並行して、大内氏の工作によって、室町幕府から、少弐氏に味方すべからずという命令が宗貞国に届きます。貞国はこれに従いました。つまり、少弐氏と宗氏の関係悪化と大内氏の政治的工作によって少弐・宗体制は崩壊したと私は考えています。



■Q&A 印刷用PDFデータ(263.03KB)
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。◎第13講 令和6年4月17日(水)
「室町期の少弐氏と朝鮮」
講師・回答:伊藤 幸司先生(九州大学大学院比較社会文化研究院教授)
講師・回答:伊藤 幸司先生(九州大学大学院比較社会文化研究院教授)
少弐氏が朝鮮との関係にそれほどまでにこだわった理由は何でしょうか。
少弐氏の朝鮮通交は、当初から対馬宗氏に依存して行われており、少弐氏は宗氏ほど朝鮮通交にはこだわっていなかったように思われます。
むしろ、朝鮮通交をすることによって、一定程度の利益を獲得できれば良いという程度のものであった可能性があります。
朝鮮通交を生命線とした宗氏とは、朝鮮通交に対する思い入れの度合いは異なっていたと考えられます。
むしろ、朝鮮通交をすることによって、一定程度の利益を獲得できれば良いという程度のものであった可能性があります。
朝鮮通交を生命線とした宗氏とは、朝鮮通交に対する思い入れの度合いは異なっていたと考えられます。



北部九州をおさえていた少弐氏が、その地の利を活かしきれず、結局、戦国大名として残れなかったのはなぜでしょうか。
大友氏や島津氏と異なり、本州から関門海峡を越えて大内氏が北部九州地域に進出してきたことが大きな要因です。室町幕府と連携しながら進出する大内氏に対して、少弐氏は有効な手段を打てず、結局、じり貧になってしまいました。一方、大友氏や島津氏は、それぞれ内部抗争などはあっても、豊後や南九州に大内氏のような強力な外的勢力が直接進出してくることはありませんでした。



朝鮮にとって、宗氏をはじめとする倭人との交易にはどのようなメリットがあったのでしょうか。
倭寇対策ということのほかに、朝鮮自身も日本との通交貿易によって入ってくる物資を必要としていた面があります。例えば、博多商人などの日本側通交者は、東南アジア産の蘇木や胡椒などを入手して朝鮮に輸出していましたが、それらは朝鮮国内でも必需品でした。



■Q&A 印刷用PDFデータ(255.53KB)
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。◎第12講 令和6年3月20日(水・祝)
「大宰府と東アジア」
講師・回答:田中 史生先生(早稲田大学文学学術院教授)
講師・回答:田中 史生先生(早稲田大学文学学術院教授)
国際交易の窓口であった大宰府には、多くの「ひと」や「もの」が入ってきました。その際に疫病も入ってきたのではないかと思いますが、そうした事例があれば教えてください。また、その対策も教えてください。
735年(天平7)、大宰府管内から流行が広がった天然痘は、翌年一旦収束しますが、737年にやはり大宰府管内から第2波が起こります。これにより都でも多くの死者を出しますが、この天然痘流行の対策に関して、最近、平城京跡の発掘調査をふまえた大変興味深い知見が示されています。この時、権力者であった藤原四氏も命を落としたことはよく知られていますが、その一人、藤原麻呂の邸宅で使用されていたとみられる食器が、邸宅外に掘られた穴に一括して廃棄されていたことがわかりました。これは感染者が使用した食器を一気に廃棄することで、感染拡大を防ごうとしたものだとみられています。この時、人々はまじないなどを盛んに行い、天然痘を防ごうとしていました。その一方で、疫病が食器などで感染拡大するという「科学的」な認識も持っていたようです。
また都では、872年正月、「逆咳病」が流行し、これが前年末にやってきた渤海使の「異土の毒気」のせいだと噂されました。この病はインフルエンザではないかともいわれています。この時の渤海使は加賀に来着しているので、大宰府と直接の関係ありませんが、古代の人々は、疫病が人の移動とともに海外からもやってくると警戒していたようです。この時は、都の内裏の建礼門前で大祓が行われました。
また都では、872年正月、「逆咳病」が流行し、これが前年末にやってきた渤海使の「異土の毒気」のせいだと噂されました。この病はインフルエンザではないかともいわれています。この時の渤海使は加賀に来着しているので、大宰府と直接の関係ありませんが、古代の人々は、疫病が人の移動とともに海外からもやってくると警戒していたようです。この時は、都の内裏の建礼門前で大祓が行われました。




日本は海に囲まれていることから、大宰府とまではいかなくても、半島や大陸と交易を行っていた場所があったのではないでしょうか。そういうところがあれば教えてください。
古代の大宰府の時代(奈良・平安時代)に限れば、講義の中でもお話したように、来航した外交使節が交易を行う場所は、主に都であったと考えられます。平安時代に商人が盛んに来航するようになると、大宰府が管理する鴻臚館、次いで博多がその中心となりました。ただし渡来商船は、博多湾までの行き帰りの寄港地、例えば唐津湾や五島列島などでも交易を行っていたとみられます。また例えば9世紀は、有明沿岸部の有力層が新羅人と通じていることが問題となったように、新羅系交易者の船は、有明海側へも入っていたと思われます。さらに最近、長崎県大村市の竹松遺跡において、9〜13世紀を前後する時期の中国陶磁器、高麗青磁、朝鮮製無釉薬陶器などを含む多くの渡来文物が出土し、注目を集めました。ここにもおそらく商船が来航していたのでしょう。私は、博多で貿易を行った渡来商人が、その後、鹿児島や喜界島へも向い、硫黄や貝殻などの南島産品の交易を行うこともあったと考えています。
また特に11世紀半ばから12世紀前半は、宋商船が北陸に来着する事例も目立ちます。その背景はまだよく分かっていませんが、消費地である都へのアクセスの良さなどが考慮されていたと考えられています。
平安時代の日本列島における国際交易の中心地は、なんといっても博多です。しかし以上に見たように、その他の地域にも交易者は渡来していました。ただ、文献史料が乏しく、その実態は謎に包まれています。日本列島では、商船の渡来や交易品の流通が、どのような環境・構造・ネットワークのもとに展開していたか、世界史と地域史の視点から読み直す必要があると感じています。
また特に11世紀半ばから12世紀前半は、宋商船が北陸に来着する事例も目立ちます。その背景はまだよく分かっていませんが、消費地である都へのアクセスの良さなどが考慮されていたと考えられています。
平安時代の日本列島における国際交易の中心地は、なんといっても博多です。しかし以上に見たように、その他の地域にも交易者は渡来していました。ただ、文献史料が乏しく、その実態は謎に包まれています。日本列島では、商船の渡来や交易品の流通が、どのような環境・構造・ネットワークのもとに展開していたか、世界史と地域史の視点から読み直す必要があると感じています。


■Q&A 印刷用PDFデータ(298.61KB)
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。◎第11講 令和6年2月17日(水)
「菅原道真と大宰府」
講師・回答:松川 博一先生(九州歴史資料館学芸調査室長)
講師・回答:松川 博一先生(九州歴史資料館学芸調査室長)
大宰府での道真公の暮らしはどのようなものだったのでしょうか?
かなり厳しい生活だったと思っていたのですが、いかがでしょうか?
かなり厳しい生活だったと思っていたのですが、いかがでしょうか?
給与である公廨の配分については、先例に従えば、大宰帥(長官:10分)の3分の1ということですので、大宰大少監(判官:3分)とほぼ同等ということになります。したがって大宰府の役人の中では5本の指に入る給与をもらっていたとみられます。食料については漢詩に「月俸」(月料)とみえますので月々の食料となる米・調味料・副食物などが支給されていた可能性が高く、そこまで食べものに困っていなかったと思われます。住まいについては、おそらく大宰権帥や大弐などの高官がかつて住んでいて、しばらく空き家となっていた官舎(館)を与えられたと考えられます。邸宅の立地や規模は権帥にふさわしいものだったと思われますが、漢詩からは手入れされておらず、かなり老朽化した建物を与えられたことがうかがえます。
いずれにいたしましても、祖父の代から上級貴族の家に生まれ、右大臣の地位まで上り詰めた菅原道真公にとっては、大宰府での生活は侘しいものだったと思われます。
いずれにいたしましても、祖父の代から上級貴族の家に生まれ、右大臣の地位まで上り詰めた菅原道真公にとっては、大宰府での生活は侘しいものだったと思われます。




大宰府が左遷の地となったのはいつ頃からのことでしょうか?
史料で確認できる古い例としては、大化5年(649)の蘇我臣日向が「筑紫大宰帥」として西下していることが挙げられます。『日本書紀』では、当時彼の赴任を「隠流(しのびながし)」と言われていたと伝えます。ただし、「隠流」については左遷との理解のほかに、ほとぼりを冷ますための栄転的な側面をもった処置との見解もあります。



■Q&A 印刷用PDFデータ(254.71KB)
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。◎第10講 令和6年1月17日(水)
「古代大宰府の仏教美術」
講師・回答:井形 進先生(九州歴史資料館学芸研究班長)
講師・回答:井形 進先生(九州歴史資料館学芸研究班長)
講座では、仏像の造像には金銅仏、塑像、乾漆像、木彫(一木造、寄木造)等があり、奈良時代に塑の技法から彫の技法へ転換したという説明がありましたが、その理由はなんでしょうか。
おっしゃる通り奈良時代の末に、日本彫刻史は捻塑的技法から彫刻的技法へと主たる技法が大きく転換しています。その転換点に位置しているのは檀像です。狭義の檀像は、香木である白檀の一材から像の全てを細部に至るまで緻密に彫り出して、香りを生かすために彩色を施さないものを言います。ただし白檀は東アジアでは産出せず、また大きくは育たないので小像しか造れません。そこで唐時代の中国で、白檀の代用材として栢木を用いてもよいとされました。これをもって材の調達がより容易になり、大きな像も造ることができるようになったのです。奈良時代の末に、この栢木を用いた広義の檀像が、唐から渡来した鑑真の周辺で造られ始めます。ちなみにここでは栢木は榧だとされたようで、唐招提寺に遺る鑑真が伴った中国人仏師が造像したと考えられる仏像は、腕等を除いて一本の榧材から彫出されています。鑑真がもたらした新しい信仰と造形の世界は、奈良時代の末の日本における信仰と造形の世界に大きな刺激を与え、唐招提寺の栢木檀像を起点としながら、榧材製で一木造の仏像が広く造像されるようになってゆきました。ただしこの時、鑑真の影響の大きさはもちろんですが、日本に古来あった樹木の聖性への意識なり、木工技術の伝統も意識しておく必要はあると思います。もとより、飛鳥時代にも木彫像は制作されており、捻塑的技法全盛期の奈良時代においても脈々と造り続けられていました。そのような伝統が、檀像思想なり鑑真の存在に刺激を受けて再び存在を大きくしたことも想定できます。いずれにしても、檀像を転換点と起点としながら、平安時代前期の榧材製で一木造の仏像の時代が始まったと言えます。そして木彫像、彫刻的技法は、平安時代後期以降は桧材製の寄木造の仏像が主となりながら、現代に至るまで造像技法の主流として続いているのです。


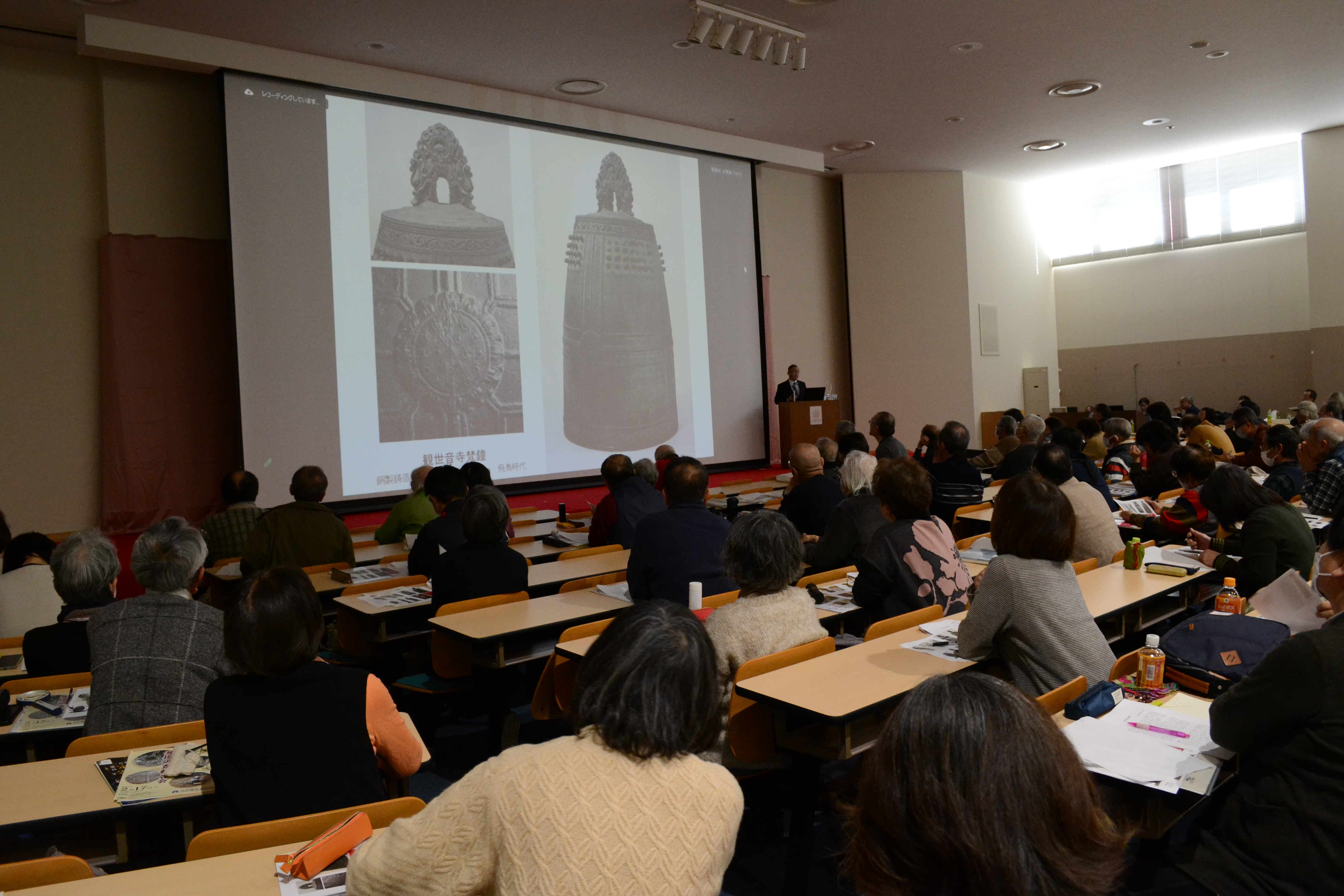
梵鐘、銅鋳仏像などの鋳造工房はどこにあったのでしょうか。
観世音寺梵鐘、観世音寺創建期の金堂主尊である銅造丈六阿弥陀如来像ということだと、はっきりと押さえてお答えすることができません。ただ一般的に、そのような大型の鋳造品は安置場所の近くに工房を設けて鋳造することが多いようですし、観世音寺境内周辺だろうとは思っています。ちなみに、観世音寺の発掘調査の成果によると、境内の東側や南東側から奈良時代の鋳造に関わる資料が見出されていますし、また鋳造に関わるものに限らず様々な出土遺物から、境内の東側には観世音寺の造営や仏像の造像などに関わる工房が存在していたのではないかと推定されたりもしています。ですので、飛鳥時代や奈良時代に大型の鋳造品を制作したのも、安置場所の直近でないならばそのあたりかな、と私は想像したりしています。



講座を聴いて、都に直結しながらも大宰府らしい仏教文化を創造したことがよく分かりましたが、その大宰府らしさの特徴はなんでしょうか。また、堂々たる丈六仏を何体も造像することができたのには、どのような要素が必要だったのでしょうか。
都に直結していながら、大宰府の周辺で都とは異なる仏教文化が花開いた背景としては、それを創造する場において、都のことのみならず太宰府の地の伝統も自然に、あるいは大切にされながら意識的に、反映されたということが考えられるのではないかと思います。ただしこの、都からの影響と在地の伝統という二つの要素ならば、太宰府の地のみならず、都以外の地方においては何処でも見受けられたことです。もちろん、それぞれの地で在地の伝統のあり方は異なりますし、都の影響の大小やその内容も異なりますので、結局どの地方においてもその地方らしい仏教文化が形成されるということにはなると思うのですが。それで、大宰府らしさを形づくった他地方にない要素と言えばやはり、なにより大陸と向き合う場にあるということからくる、大海の向こうにある世界への意識や、中国や朝鮮半島の国々をはじめとする異国との実際の交流を考えるべきだと思います。他にない意識は他にない造形を生みますし、交流すれば必ずお互いに多かれ少なかれ影響を受けます。大宰府周辺の仏教文化の他にはない個性は、都からの影響、大陸からの直接的な影響、在地の伝統の三要素が絡み合いながら、その時々その場その場の造形に結晶することから生まれていると考えています。具体的な様相については、それぞれの作品や作品が所在する場それぞれで、個別に考えてゆくべきことだと思いますが、大宰府らしさの背景を端的に言うならば、他地方にはない要素をもち、彩りが一段と豊かであるということになろうかと思います。
あと、丈六像を何体も、しかも最新の作風と技法で造像することができたことについては、まずは大宰府周辺にそれを可能にする充実した工房の存在がなければなりません。そして現存作例に加えて史料からも、事実それは存在していたと考えることができるのですが、ではそのような工房が存在することができる背景です。高い造形の水準を維持しながら大規模な造像を継続してゆくことには、並外れて充実した人的環境や経済力が必要になります。このことについても、時代によって作品によって個別具体的に考えてゆかねばなりませんが、しかしいずれにしても大づかみに言うならば、やはり大宰府の大きな力と都直結のあり方を想定するべきだと思います。古代九州において大宰府の存在は、極めて大きな意義をもっていたのだと思います。
あと、丈六像を何体も、しかも最新の作風と技法で造像することができたことについては、まずは大宰府周辺にそれを可能にする充実した工房の存在がなければなりません。そして現存作例に加えて史料からも、事実それは存在していたと考えることができるのですが、ではそのような工房が存在することができる背景です。高い造形の水準を維持しながら大規模な造像を継続してゆくことには、並外れて充実した人的環境や経済力が必要になります。このことについても、時代によって作品によって個別具体的に考えてゆかねばなりませんが、しかしいずれにしても大づかみに言うならば、やはり大宰府の大きな力と都直結のあり方を想定するべきだと思います。古代九州において大宰府の存在は、極めて大きな意義をもっていたのだと思います。



■Q&A 印刷用PDFデータ(288.30KB)
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。◎第9講 令和5年12月20日(水)
「大宰府都城の復元」
講師・回答:井上 信正先生(太宰府市教育委員会文化財課保護活用係長)
講師・回答:井上 信正先生(太宰府市教育委員会文化財課保護活用係長)
福岡市にある鴻臚館跡と太宰府市の客館跡とでは、どのような役割分担があったのでしょうか。
講演で話をしましたように、難波館(大阪)と京内客館の関係が、筑紫館と大宰府条坊内客館(以下、条坊内客館)との間にもあったと考えています。難波館と京内客館それぞれの役割を伺う資料がないため想像するしかありませんが、船頭らは難波館・筑紫館など沿岸部の客館に滞在し、京や大宰府に向かった使節団は京内客館・条坊内客館に滞在したことは十分考えられるところです。
さて、条坊内客館が設置された当初(8世紀前半)の筑紫館(鴻臚館2期)では、北館・南館とも、布掘りと呼ばれる溝状の基礎構造をもつ塀で囲まれた空間しか見つかっておらず、内部構造がよくわかっていません。ただこのころの館の裾には石垣が設けられており、大宰府政庁使用瓦(鴻臚館式瓦)の出土量も多いことから、それなりの施設があったとして、掘立柱建物よりも遺構が消失しやすい礎石建物で構成された施設だった、との想定がなされています。
ですが、講演で説明しましたように、8世紀前半では礎石を使った官衙施設は特別です。条坊内客館は掘立柱建物であるため、筑紫館(鴻臚館2期)も掘立柱建物であれば自然だと思うのですが、それが見つからないとなると、船待ちのための簡易な宿泊施設しかなかったと考えるか、筑紫館の方が格上となる(つまり何らかの役割をもった)礎石建物があったと考えるか、両極端ですが、いずれかだろうと思います。施設の性格を大きく決定づける礎石建物が存在したと言い切ることに、私は躊躇を感じます。
唯一遺構として確かな「布掘り基礎の塀」がどのような構造物に復元ができるかによりますが、礎石建物と布掘り基礎の構造物とは、ミスマッチな組み合わせのようにも思います。この点は建築が専門でない私には判断がつきませんし、また大宰府政庁使用瓦(鴻臚館式瓦)の出土量が多い点をどのように理解するかという課題はありますが、遺構の現状をみると、鴻臚館1期北館(掘立柱塀がめぐる施設)の利用想定同様に、簡易な建物による宿泊施設だったと考えたいところです。
文献史料がないため、遺跡のあり方から施設の役割を類推するしかありませんが、大宰府条坊内客館の発見・研究は、このように筑紫館(鴻臚館2期)の遺跡評価にも影響を与えていると言えます。両館の関係については、今後も注目していきたいと思います。
さて、条坊内客館が設置された当初(8世紀前半)の筑紫館(鴻臚館2期)では、北館・南館とも、布掘りと呼ばれる溝状の基礎構造をもつ塀で囲まれた空間しか見つかっておらず、内部構造がよくわかっていません。ただこのころの館の裾には石垣が設けられており、大宰府政庁使用瓦(鴻臚館式瓦)の出土量も多いことから、それなりの施設があったとして、掘立柱建物よりも遺構が消失しやすい礎石建物で構成された施設だった、との想定がなされています。
ですが、講演で説明しましたように、8世紀前半では礎石を使った官衙施設は特別です。条坊内客館は掘立柱建物であるため、筑紫館(鴻臚館2期)も掘立柱建物であれば自然だと思うのですが、それが見つからないとなると、船待ちのための簡易な宿泊施設しかなかったと考えるか、筑紫館の方が格上となる(つまり何らかの役割をもった)礎石建物があったと考えるか、両極端ですが、いずれかだろうと思います。施設の性格を大きく決定づける礎石建物が存在したと言い切ることに、私は躊躇を感じます。
唯一遺構として確かな「布掘り基礎の塀」がどのような構造物に復元ができるかによりますが、礎石建物と布掘り基礎の構造物とは、ミスマッチな組み合わせのようにも思います。この点は建築が専門でない私には判断がつきませんし、また大宰府政庁使用瓦(鴻臚館式瓦)の出土量が多い点をどのように理解するかという課題はありますが、遺構の現状をみると、鴻臚館1期北館(掘立柱塀がめぐる施設)の利用想定同様に、簡易な建物による宿泊施設だったと考えたいところです。
文献史料がないため、遺跡のあり方から施設の役割を類推するしかありませんが、大宰府条坊内客館の発見・研究は、このように筑紫館(鴻臚館2期)の遺跡評価にも影響を与えていると言えます。両館の関係については、今後も注目していきたいと思います。




条坊に設けられた溝(側溝)はどのような役割をもっていたのでしょうか。もし水を流すための溝であったとすれば、その勾配などを考慮する測量技術などもあったのでしょうか。
条坊側溝については、以前は、発掘担当者の間で、排水路としての機能の検討(平城宮の排水ルートの研究に倣った検討)もあったように思います。
わたくしは、条坊側溝は滞水・流水を前提にしたものではなく、基本的には路面維持と区画のためと思います。よって水源確保は必要ありません。ただ排水が必要な場所はありますので、堰等を必要とした可能性はあります。蔵司南地区ではかなり排水処理が必要だったようで、木樋も出土していたと思いますが、これと堰がセットになっている可能性はあると思います。
側溝を使った流水排水が考えられるのは、御笠川以北と鷺田川以南です。山からの排水処理が必要だからです。大宰府展示館の石組み溝は左郭一坊路に関わる排水施設とみています。なお流水が多いところでは経年で路面全体が下がり、大溝のようになってしまった事例もあります。
一方で、流水による排水をしていない事例は、御笠川と鷺田川の間(条坊の中央部)ではよく見られます。理由は、この付近の地盤(地山)にあります。まず地盤が流水に耐えられないことです(すぐ溝壁がくずれる)。もう一つは、地下に厚い砂堆積(旧宝満川から博多に流れる流路があった古い時代の堆積)があり、地中に染み込ませて排水することが可能であることです。この一帯では、互いにつながっていない細長い溝が連続して側溝となっている場所もあります。まさに路面維持と区画のための側溝だということがわかります。
測量技術については、遺跡を通してみる都市設計は驚くほどの精度をもっていますし、学校院に測量を扱う算師が置かれていることからも、そうした技術はあったものと考えています。
わたくしは、条坊側溝は滞水・流水を前提にしたものではなく、基本的には路面維持と区画のためと思います。よって水源確保は必要ありません。ただ排水が必要な場所はありますので、堰等を必要とした可能性はあります。蔵司南地区ではかなり排水処理が必要だったようで、木樋も出土していたと思いますが、これと堰がセットになっている可能性はあると思います。
側溝を使った流水排水が考えられるのは、御笠川以北と鷺田川以南です。山からの排水処理が必要だからです。大宰府展示館の石組み溝は左郭一坊路に関わる排水施設とみています。なお流水が多いところでは経年で路面全体が下がり、大溝のようになってしまった事例もあります。
一方で、流水による排水をしていない事例は、御笠川と鷺田川の間(条坊の中央部)ではよく見られます。理由は、この付近の地盤(地山)にあります。まず地盤が流水に耐えられないことです(すぐ溝壁がくずれる)。もう一つは、地下に厚い砂堆積(旧宝満川から博多に流れる流路があった古い時代の堆積)があり、地中に染み込ませて排水することが可能であることです。この一帯では、互いにつながっていない細長い溝が連続して側溝となっている場所もあります。まさに路面維持と区画のための側溝だということがわかります。
測量技術については、遺跡を通してみる都市設計は驚くほどの精度をもっていますし、学校院に測量を扱う算師が置かれていることからも、そうした技術はあったものと考えています。




■Q&A 印刷用PDFデータ(115.83KB)
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。◎第8講 令和5年11月15日(水)
「筑紫万葉の世界」
講師・回答:月野 文子先生(福岡女子大学名誉教授)
講師・回答:月野 文子先生(福岡女子大学名誉教授)
今回の講義では、筑紫万葉の見方が変わりました。旅人・憶良を中心とする「筑紫万葉の世界」が、実は大陸・半島と密接につながっていたということがよく理解できました。
そこで、官人たちが参考とした文献(作品)にはどのようなものがあったのでしょうか。律令成立以前からすでに漢詩文の素養が求められる状況であったとすると、かなりの写本が日本国内にあったと考えてよいのでしょうか。
そこで、官人たちが参考とした文献(作品)にはどのようなものがあったのでしょうか。律令成立以前からすでに漢詩文の素養が求められる状況であったとすると、かなりの写本が日本国内にあったと考えてよいのでしょうか。
奈良時代に如何なる書物が入ってきていたのか全体像はつかめません。我国へ伝来した漢籍については『日本国見在書目録』(わが国最古の漢籍目録、寛平3年(891)頃までに成立)が参考になりますが、目録記載の漢籍が何時どのような経路を辿って伝わったのかは定かではありません。漢籍の招来時期を考える際に、遣唐使船が目安とされることが多いようですが、別ルートで帰国する留学生・留学僧や遣新羅使船、朝鮮半島から帰化した人々がもたらした漢籍も少なくなかったと思われます。
この時代、とくに注意しておきたいのは『芸文類聚』(中国で編纂された類書(一種の百科事典)、624年成立)の利用です。本書は、項目として掲げる事物について、古辞書や経書などの記述を引用し、その後にその事物に関する詩文を載せているため、故事や文学表現を効率よく学ぶことが出来ました。
こうした漢籍の伝来については、①上代の作品内部(思想・語句など)から影響を及ぼした原典を探る、②文献の記載を参考に推測を重ねる、という地味な作業から、舶載されていたであろう漢籍を推定していくのですが、「〇〇に曰く」などとあっても、前述の『芸文類聚』からの孫引きである可能性も否定しきれません。
講座最後の「今日のポイント」で取り上げた紀末茂の場合は、誰がみても張正見の「釣竿篇」と酷似しており、また『日本国見在書目録』にも「張正見集」が記載されていますので、この集が紀末茂の活躍した奈良時代初期に伝来していたことは間違いありませんが、その時期や経路は不明と言わざるを得ません。
なお、紀末茂の詩については、月野の論文(『上代文学』119号、2017年)
「紀末茂「臨水観魚」誌が描く朝隠ー張正見詩から「渭水終須ト、滄浪徒自吟」を削除した理由」をご参照ください。
この時代、とくに注意しておきたいのは『芸文類聚』(中国で編纂された類書(一種の百科事典)、624年成立)の利用です。本書は、項目として掲げる事物について、古辞書や経書などの記述を引用し、その後にその事物に関する詩文を載せているため、故事や文学表現を効率よく学ぶことが出来ました。
こうした漢籍の伝来については、①上代の作品内部(思想・語句など)から影響を及ぼした原典を探る、②文献の記載を参考に推測を重ねる、という地味な作業から、舶載されていたであろう漢籍を推定していくのですが、「〇〇に曰く」などとあっても、前述の『芸文類聚』からの孫引きである可能性も否定しきれません。
講座最後の「今日のポイント」で取り上げた紀末茂の場合は、誰がみても張正見の「釣竿篇」と酷似しており、また『日本国見在書目録』にも「張正見集」が記載されていますので、この集が紀末茂の活躍した奈良時代初期に伝来していたことは間違いありませんが、その時期や経路は不明と言わざるを得ません。
なお、紀末茂の詩については、月野の論文(『上代文学』119号、2017年)
「紀末茂「臨水観魚」誌が描く朝隠ー張正見詩から「渭水終須ト、滄浪徒自吟」を削除した理由」をご参照ください。




講義の中で取り上げられた、漢音と呉音の関係について教えてください。日本での呉音使用は仏教関係用語に限定されますか。
時代・地域・音韻の変化等が絡む問題ですが、漢音・呉音に限定した大雑把な答であることをご了承ください。
漢音・呉音・唐宋音は日本における漢字音の呼称です。「漢音」は中国北西部(長安周辺地域)の中国語の発音を指し、「呉音」は長江流域(南京周辺地域)の中国語の発音を指します。(全ての漢字音が異なる訳ではありません)
かつて呉と呼ばれていた地域では、南朝(六朝)の文化が長きに亘って栄えており、その時代の都周辺の発音が朝鮮半島を経由して我国へ伝わりました。これが呉音です。朝鮮半島の任那や百済など我国と関係の深かった地域は、黄海を隔てて呉音の地域と向かい合っており、船舶による交易等の交流もありました。懐風藻の序文にも見られるように、古い時代の漢字・漢語、漢籍の多くは半島経由で我国へもたらされていたわけです。(その意味では、日本に入ってきた呉音は既に半島訛であり、それが更に日本訛で変化し、本来の中国語音とは相当の隔たりがあったと思われます)
六世紀末になると、北朝系から出た隋・唐が中国を統一し、その都長安地方の発音が標準とされるようになります。これが漢音です。我国でも外交上の必要に迫られて漢音を奨励することになりますが、国内において浸透していた呉音を払拭することは出来ず、混用(事実上の併用)が続くことになります。朝廷は、大学寮にネイティブの音博士を採用し、帰国した留学生に弟子を取らせるなどして漢音を学ばせようとしましたが、その効果は限定的だったようです。(新羅でも同様の問題はあったと想像できます)
また、九世紀末に、遣唐使が廃止されると漢音に拘る必要性は低下し、さらに後代には僧侶や交易商人等によって、あらたに呉音系の発音や沿岸部の方言も入って来ることになります。
なお、呉音は仏教関連に限ったことではありません。漢籍の『論語』(ろんご)、『礼記』(らいき)、『詩経』(しきょう)、『文選』(もんぜん)・・・これらは所謂「呉音」読みです。
漢音・呉音・唐宋音は日本における漢字音の呼称です。「漢音」は中国北西部(長安周辺地域)の中国語の発音を指し、「呉音」は長江流域(南京周辺地域)の中国語の発音を指します。(全ての漢字音が異なる訳ではありません)
かつて呉と呼ばれていた地域では、南朝(六朝)の文化が長きに亘って栄えており、その時代の都周辺の発音が朝鮮半島を経由して我国へ伝わりました。これが呉音です。朝鮮半島の任那や百済など我国と関係の深かった地域は、黄海を隔てて呉音の地域と向かい合っており、船舶による交易等の交流もありました。懐風藻の序文にも見られるように、古い時代の漢字・漢語、漢籍の多くは半島経由で我国へもたらされていたわけです。(その意味では、日本に入ってきた呉音は既に半島訛であり、それが更に日本訛で変化し、本来の中国語音とは相当の隔たりがあったと思われます)
六世紀末になると、北朝系から出た隋・唐が中国を統一し、その都長安地方の発音が標準とされるようになります。これが漢音です。我国でも外交上の必要に迫られて漢音を奨励することになりますが、国内において浸透していた呉音を払拭することは出来ず、混用(事実上の併用)が続くことになります。朝廷は、大学寮にネイティブの音博士を採用し、帰国した留学生に弟子を取らせるなどして漢音を学ばせようとしましたが、その効果は限定的だったようです。(新羅でも同様の問題はあったと想像できます)
また、九世紀末に、遣唐使が廃止されると漢音に拘る必要性は低下し、さらに後代には僧侶や交易商人等によって、あらたに呉音系の発音や沿岸部の方言も入って来ることになります。
なお、呉音は仏教関連に限ったことではありません。漢籍の『論語』(ろんご)、『礼記』(らいき)、『詩経』(しきょう)、『文選』(もんぜん)・・・これらは所謂「呉音」読みです。




■Q&A 印刷用PDFデータ(112.89KB)
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。◎第7講 令和5年10月18日(水)
「古代大宰府の宗教世界」
講師・回答:森 弘子先生(大宰府アカデミー・令和編副学長、福岡県文化財保護審議会会長)
講師・回答:森 弘子先生(大宰府アカデミー・令和編副学長、福岡県文化財保護審議会会長)
鎮護国家の時代、日本と新羅は互いに調伏を目的として、呪詛が行われたのことですが、国交はなかったのでしょうか?また互いの国の情報はどのように入手していたのでしょうか?
まず、お尋ねの日本・新羅の国交という点です。それが両国の公的使節の往来ということであれば、それは新羅からは遣日使(日本側の史料では新羅使)が、日本からは遣新羅使が任命・派遣されていますので、国交はあったといえるでしょう。こうした往来や、また遣唐使、遣渤海使の派遣などによって情報を入手していたと考えられます。
ただし外交交渉のなかでは、日本と新羅との間にはさまざまな軋轢が生じています。日本は、その際に交わされる新羅からの国書や口頭による報告などに、従来の通例によらず、無礼な点があるとしばしば指摘しており、天平宝字年間(757~765)には、藤原仲麻呂政権による新羅征討計画もあらわれてくるのです(この計画は、仲麻呂の失脚によって実現はしませんでした)。新羅からの公的使節は宝亀10年(779)の来航が、結果的には最後になります。
そうした過程のなかで、講座で紹介した宝亀5年(774)の四王寺山における新羅呪詛に対抗する仏像造立・寺院建立ということがみられるのです。平安時代前期までは朝鮮式山城としての大野城と、四王寺の記録とが並行してあらわれますが、それ以降は四王寺(あるいは四王院)のそれが主となります。こうした点を考えると、講座でも申しましたように、宗教的な場としての四王寺山がもっと注目されるべきだと考えているのです。
ただし外交交渉のなかでは、日本と新羅との間にはさまざまな軋轢が生じています。日本は、その際に交わされる新羅からの国書や口頭による報告などに、従来の通例によらず、無礼な点があるとしばしば指摘しており、天平宝字年間(757~765)には、藤原仲麻呂政権による新羅征討計画もあらわれてくるのです(この計画は、仲麻呂の失脚によって実現はしませんでした)。新羅からの公的使節は宝亀10年(779)の来航が、結果的には最後になります。
そうした過程のなかで、講座で紹介した宝亀5年(774)の四王寺山における新羅呪詛に対抗する仏像造立・寺院建立ということがみられるのです。平安時代前期までは朝鮮式山城としての大野城と、四王寺の記録とが並行してあらわれますが、それ以降は四王寺(あるいは四王院)のそれが主となります。こうした点を考えると、講座でも申しましたように、宗教的な場としての四王寺山がもっと注目されるべきだと考えているのです。



香椎宮では、仲哀天皇が亡くなったということから、仲哀天皇の廟という性格があるのでしょうか?
『筑前国風土記』逸文には、(大宰府の官人などが)筑紫国に赴任すれば、まず香椎宮に参謁するのが例とされており、中央政府にとってもきわめて重要な場所であったことが知られます。同宮の縁起である『香椎宮編年記』には神亀元年(728)の創建と記されますが、確実な初見例は同5年11月に大宰帥大伴旅人・大弐小野老・豊前守宇努男人らが参拝した記事(『万葉集』巻6)なのです。
祭神は仲哀天皇、神功皇后です。ご指摘のように、仲哀天皇が香椎宮で亡くなったという伝承(『日本書紀』仲哀天皇紀、『古事記』仲哀天皇段)があり、古くから香椎宮を仲哀天皇の廟とする説もありましたが、その後のさまざまな研究を承けて、現在、学界においては神功皇后の廟とする説が定説になっています。
もちろん、神功皇后は実在の人物ではありませんが、おそらくは、この地における長い間の半島との緊張関係の記憶、またそのような中から生まれた伝説などから、新羅に対する勝利の女神として創出されたものと考えられます。香椎宮の地は、磐井の乱の後、息子の葛子が献上した粕屋屯倉の地で、磐井が新羅との交流をするための港だったという考え方もあり、そのような重要な場所であったからこそ、ここに中央政府によって新羅に対抗するための香椎宮(香椎廟)が建てられ、そしてそのことには、内政的な意味もあったのではないかと考えています。
祭神は仲哀天皇、神功皇后です。ご指摘のように、仲哀天皇が香椎宮で亡くなったという伝承(『日本書紀』仲哀天皇紀、『古事記』仲哀天皇段)があり、古くから香椎宮を仲哀天皇の廟とする説もありましたが、その後のさまざまな研究を承けて、現在、学界においては神功皇后の廟とする説が定説になっています。
もちろん、神功皇后は実在の人物ではありませんが、おそらくは、この地における長い間の半島との緊張関係の記憶、またそのような中から生まれた伝説などから、新羅に対する勝利の女神として創出されたものと考えられます。香椎宮の地は、磐井の乱の後、息子の葛子が献上した粕屋屯倉の地で、磐井が新羅との交流をするための港だったという考え方もあり、そのような重要な場所であったからこそ、ここに中央政府によって新羅に対抗するための香椎宮(香椎廟)が建てられ、そしてそのことには、内政的な意味もあったのではないかと考えています。



■Q&A 印刷用PDFデータ(147.91KB)
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。◎第6講 令和5年9月20日(水)
「大宰府の出土文字資料」
講師・回答:酒井 芳司氏(九州歴史資料館参事補佐、学芸員)
講師・回答:酒井 芳司氏(九州歴史資料館参事補佐、学芸員)
前回(第5講)の佐藤信先生のお話の中で、大宰府から平城京へ向けて送られた木簡は(敢えて)広葉樹の材を使用していたとのことでした。酒井先生はその理由をどのようにお考えでしょうか。
たしかに、都で出土する西海道諸国からの木簡には、ほぼすべてに広葉樹が用いられています。これらは諸国でではなく、大宰府で作成されたものと考えられます。一方、西海道諸国から大宰府に送られた木簡には、ほぼ例外なく針葉樹が用いられています。つまり、九州で作成された木簡に、広く広葉樹が用いられていたわけではなく、広葉樹の木簡は、大宰府から京進されるもののためのみに作成されたのです。
さて、その理由については、ほかに類例もないことからよく分かりません。ただ、広葉樹は針葉樹に比べて堅牢なことから、製作・加工が難しいかわりに、繊細、丁寧な文字を書くことができます。つまり、そうした木簡を作るために敢えて広葉樹を用いたと考えられます。
私は、平城宮跡から出土した大宰府からの木簡のなかに「筑紫大宰進上……」と記されたものがあることに注目しています。この「筑紫大宰」とは「大宰府」の前身に当たる古い表記で、そこに大宰府、あるいは筑紫大宰が、京に進上することに特別な意味をもたせていたのではないか、そのためにわざわざ広葉樹の木簡を用いたのではないか、と考えています。
さて、その理由については、ほかに類例もないことからよく分かりません。ただ、広葉樹は針葉樹に比べて堅牢なことから、製作・加工が難しいかわりに、繊細、丁寧な文字を書くことができます。つまり、そうした木簡を作るために敢えて広葉樹を用いたと考えられます。
私は、平城宮跡から出土した大宰府からの木簡のなかに「筑紫大宰進上……」と記されたものがあることに注目しています。この「筑紫大宰」とは「大宰府」の前身に当たる古い表記で、そこに大宰府、あるいは筑紫大宰が、京に進上することに特別な意味をもたせていたのではないか、そのためにわざわざ広葉樹の木簡を用いたのではないか、と考えています。



今回の講座では、木簡などの出土文字資料を中心に興味深いお話しを伺うことができました。そこで質問ですが、そもそも日本人が漢字を使うようになったのはおおよそいつ頃からのことでしょうか。
これもはっきりした年代を示すことは難しいのですが、次のように考えられています。
日本列島における漢字の使用例は、早くは志賀島で出土した金印「漢委奴国王」がありますが、これは当時の日本人が漢字を使ったものではなく、西暦57年に、後漢の光武帝から贈られたものがこれに当たると考えられています。
漢字と漢文体、また固有名詞には音訳を用いて、まとまった文章を綴ったものとしては稲荷山古墳出土鉄剣銘があり、これにみえる「辛亥年」は西暦471年と考えられており、こうした形を日本列島における漢字使用の始まりと位置づけてよければ、それはおおよそ5世紀ということになります。
こうしたなかで、その書写材料として木簡が用いられることになるわけです。現在のところ、木簡の確実な使用例としては七世紀以後のものしか確認されていませんが、私は講座の中でも申し上げましたように、日本書紀の記事などから6世紀半ばからではないかと考えています。
日本列島における漢字の使用例は、早くは志賀島で出土した金印「漢委奴国王」がありますが、これは当時の日本人が漢字を使ったものではなく、西暦57年に、後漢の光武帝から贈られたものがこれに当たると考えられています。
漢字と漢文体、また固有名詞には音訳を用いて、まとまった文章を綴ったものとしては稲荷山古墳出土鉄剣銘があり、これにみえる「辛亥年」は西暦471年と考えられており、こうした形を日本列島における漢字使用の始まりと位置づけてよければ、それはおおよそ5世紀ということになります。
こうしたなかで、その書写材料として木簡が用いられることになるわけです。現在のところ、木簡の確実な使用例としては七世紀以後のものしか確認されていませんが、私は講座の中でも申し上げましたように、日本書紀の記事などから6世紀半ばからではないかと考えています。


■Q&A 印刷用PDFデータ(76.53KB)
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。◎第5講 令和5年8月16日(水)
「大宰府機構の成立とその変遷」
講師・回答:佐藤 信氏(東京大学名誉教授、くまもと文学・歴史館館長、横浜市歴史博物館館長)
講師・回答:佐藤 信氏(東京大学名誉教授、くまもと文学・歴史館館長、横浜市歴史博物館館長)
講座の中で、先生は平城京における「調邸」の存在を手がかりに、大宰府における管内諸国の出張所の存在を推定されていましたが、もう少し具体的に教えてください。
調邸というのは、諸国から運んできた調物を都、またはその周辺で一時的に保管するための施設と考えられ、講座のなかでも申しましたように、いわば各国の都における出張所のようなものです。大宰府の場合、管内諸国の調物は、他の諸国とは違って京進されずに大宰府へと集積され、その一部が大宰府から都へと送られたことが知られています。とすれば、確実な史料はありませんが、管内諸国の調邸は、大宰府、ないしその周辺に置かれた可能性が想定できると思います。講座の中では、『万葉集』にみえる、帥大伴旅人邸で催された梅花の宴に参列した管内諸国官人の中に、こうした調邸に詰めていた人物が含まれているのではないかと推測してみたのです。




講座の中で、古代の役所における給食機能についてふれておられましたが、そうした給食のための施設は発掘調査などで具体的にわかっているのでしょうか。大宰府ではどのあたりにあったかわかりますか。
古代において、こうした給食機能を担った施設、すなわち台所にあたる施設は「厨(くりや)」と呼ばれています。その実際の姿はなかなかつかめませんが、都では平城宮東院地区の発掘調査で井戸や複数の竈痕跡など、この「厨」に関連する可能性の高い遺構が見つかっています。しかし、残念ながら大宰府ではこうした遺構はまだ見つかっていませんが、西鉄二日市駅に隣接する「特別史跡大宰府跡客館地区(客館跡)」は、主に新羅から来航した外交施設の安置・供給に使われたと考えられています。その客館敷地内の北西部では、国際色豊かな高級食器類、容器類などが出土し、また井戸も数基まとまって確認されることから、給食や給仕に関係するエリアと推定されています。講座でも申しましたように、この場所では養老職員令大宰府条にその名がみえる「主厨」が、その給食に関わっていたのであろうと想像できます。




■Q&A 印刷用PDFデータ(80.76KB)
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。◎第4講 令和5年7月19日(水)
「朝鮮式山城~水城・大野城・基肄城・鞠智城~」
講師・回答:赤司 善彦氏(大野城心のふるさと館館長)
講師・回答:赤司 善彦氏(大野城心のふるさと館館長)
赤司先生が講座で述べられたように大野城・基肄城の築城が650年から着手されたとすると、その目的、また契機は何でしょうか。
『日本書紀』白雉二年(651)条に新羅が唐の礼服の制度など各種の唐風化を推進したことで、新羅使の来朝の折に、唐服を着用していたことを詰問し追い返したと記しています。続けてここで新羅を懲らしめるために難波津から筑紫の海に船をいっぱいに浮かべて新羅を呼びつけることを提案しています。
たんに唐風化した新羅を責めたのではなく、唐が朝鮮半島の争いに介入することを阻止しようとしたとする見方もあります。この記事をもって実際に軍事プレゼンスに及んだとは思えませんが、新羅を仮想敵国と位置づけてその対抗措置として山城を築城し軍事拠点を形成したと考えられないでしょうか。
またたとえば、640年代後半の渟足柵・磐船柵造営という東北地域における軍事的な動向との連動ということも考えられるのではないかと思います。このことは、唐の東アジア遠征を受けたものともされていますから、それが南方でもあったのではないか、とみるのです。つまり、ここでも前述した唐による朝鮮半島への介入という対外的な危機を受け止めたということもあるのかもしれません。
いずれにしても確定的とは言えず、今後の研究によって深めていかなければならない点だと思います。
たんに唐風化した新羅を責めたのではなく、唐が朝鮮半島の争いに介入することを阻止しようとしたとする見方もあります。この記事をもって実際に軍事プレゼンスに及んだとは思えませんが、新羅を仮想敵国と位置づけてその対抗措置として山城を築城し軍事拠点を形成したと考えられないでしょうか。
またたとえば、640年代後半の渟足柵・磐船柵造営という東北地域における軍事的な動向との連動ということも考えられるのではないかと思います。このことは、唐の東アジア遠征を受けたものともされていますから、それが南方でもあったのではないか、とみるのです。つまり、ここでも前述した唐による朝鮮半島への介入という対外的な危機を受け止めたということもあるのかもしれません。
いずれにしても確定的とは言えず、今後の研究によって深めていかなければならない点だと思います。



古代山城の倉庫群のお話がありましたが、築城当初には倉庫群は想定されておらず、軍事的な機能をもった山城から備蓄基地へと変わったことで、倉庫群が建てられたのでしょうか。
講座の中でも申し上げましたが、山城、特に筑紫城(大野城・基肄城・鞠智城)の中の建物については、その移り変わりを、私は次のように考えています。つまり築城直後の七世紀末に、長倉という大規模な倉庫が建造されます。その後奈良時代になると、三間×五間の礎石高床倉庫の造営があり、さらに九世紀以降、三間×四間のやや小規模な倉庫が建造されていきます。しかもこれは建替ではなく、増築されているのです。これは、主に大野城の場合ですが、基肄城も奈良時代はほぼ同じ動きで、鞠智城はやや様相が異なりますが、ほぼ同じように倉庫群の造営・拡張が行われています。
この整理によれば、倉庫群は築城当初から設けられていたとみなければならないでしょう。そして、それは軍事的な兵站機能をもっていたと考えられます。畿内・瀬戸内海沿岸の山城が停廃されていく中、八世紀以降も存続した筑紫城(大野城・基肄城・鞠智城)は、そうした兵站機能を維持しつつ、その主要な役割を、行政的な地方支配に関わるとみられる備蓄機能へと変化させていったものと考えています。
この整理によれば、倉庫群は築城当初から設けられていたとみなければならないでしょう。そして、それは軍事的な兵站機能をもっていたと考えられます。畿内・瀬戸内海沿岸の山城が停廃されていく中、八世紀以降も存続した筑紫城(大野城・基肄城・鞠智城)は、そうした兵站機能を維持しつつ、その主要な役割を、行政的な地方支配に関わるとみられる備蓄機能へと変化させていったものと考えています。



■Q&A 印刷用PDFデータ(74.27KB)
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。◎第3講 令和5年6月21日(水)
「白村江戦」
講師・回答:森 公章氏(東洋大学教授)
講師・回答:森 公章氏(東洋大学教授)
磐瀬(行)宮・長津宮、朝倉橘広庭宮の所在地について
斉明天皇が征西のために筑紫に下った際に留まったとされる磐瀬(行)宮・長津宮の所在地はどこだと考えられていますか。また朝倉橘広庭宮はどこでしょうか。
磐瀬(行)宮・長津宮について、『日本書紀』によれば、斉明天皇一行は「娜大津」(博多)に着くと、まず「磐瀬行宮」に入ったとされ、斉明天皇はその名を「長津」と改めたとみえますから、この「磐瀬(行)宮」は、その後の『日本書紀』に登場する「長津宮」と同じ場所だと考えられます。この宮については、現在までのところ、その遺跡は発見されていませんが、その地名などから現在の西日本鉄道福岡天神大牟田線の高宮駅西側丘陵裾部に比定する説があります。
朝倉橘広庭宮は、古くはこれを土佐国に比定する説などもありました。近年では、現在の大宰府政庁の場所(発掘調査により検出された政庁Ⅰ-1期)と考える説が呈されています。また地名の観点から、これを現在の朝倉地域に求める説も古くからあります。『日本書紀』によると「朝倉社」(麻底良山山頂に鎮座する麻氐良布神社と考えられています)の近くに所在したと推定されることから、その候補地として朝倉市須川(旧朝倉町大字須川)、同市山田(旧朝倉町大字山田)、同市杷木志波(旧杷木町志波)の三地区があげられていましたが、1990年代の九州横断道建設の際の発掘調査により、志波地区から大規模建物跡群が発見され、これらが朝倉橘広庭宮に関係する遺跡ではないか、とされ、朝倉地区の中では、この志波地区がもっとも有力と考えられています。
朝倉橘広庭宮は、古くはこれを土佐国に比定する説などもありました。近年では、現在の大宰府政庁の場所(発掘調査により検出された政庁Ⅰ-1期)と考える説が呈されています。また地名の観点から、これを現在の朝倉地域に求める説も古くからあります。『日本書紀』によると「朝倉社」(麻底良山山頂に鎮座する麻氐良布神社と考えられています)の近くに所在したと推定されることから、その候補地として朝倉市須川(旧朝倉町大字須川)、同市山田(旧朝倉町大字山田)、同市杷木志波(旧杷木町志波)の三地区があげられていましたが、1990年代の九州横断道建設の際の発掘調査により、志波地区から大規模建物跡群が発見され、これらが朝倉橘広庭宮に関係する遺跡ではないか、とされ、朝倉地区の中では、この志波地区がもっとも有力と考えられています。


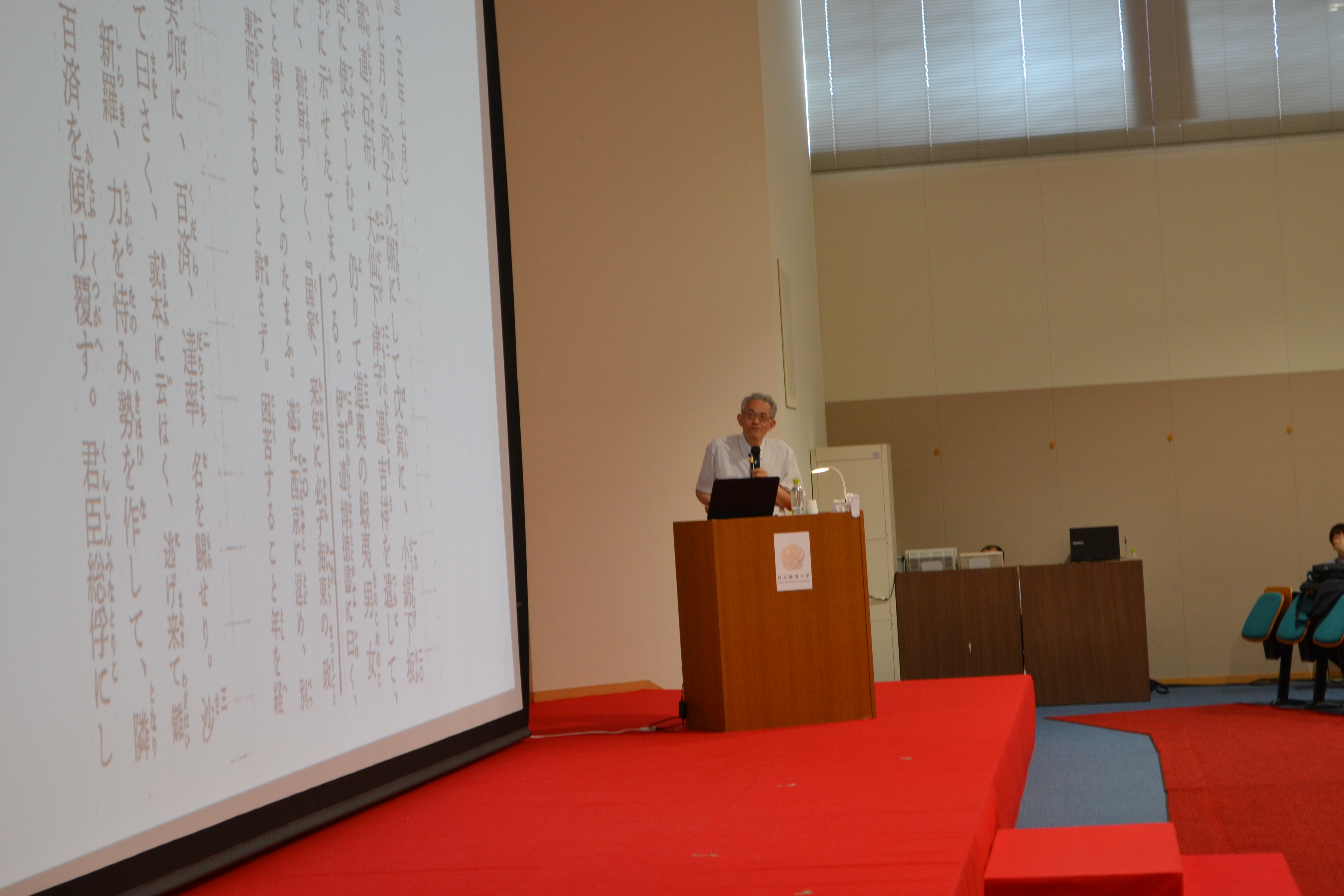
倭国船の構造について
白村江戦に出陣した倭国船はどのような船だったのでしょうか。
まず、『日本書紀』によれば、唐側の船は「戦船(いくさぶね)」と記されています。いわゆる戦艦で、鉄板が張ってあり防御性に優れ、また櫓を設けて、そこから射かけるなどの攻撃が可能なように造られていました。一方、日本側のそれは、中国側の史料である『旧唐書』劉仁軌伝には、単に「舟」と書かれており、唐から見れば、小舟にすぎない貧弱な兵備であったと考えられます。その倭国船が具体的にどのような構造の船であったかは、よくわかりませんが、古墳から出土している船形埴輪などから推定すると、木製の丸木舟(刳船)に竪板(舷側板)を追加した、準構造船と呼ばれる様式の船だったのではないか、と考えられます。こうした点を踏まえて作成したのが、講義でも紹介しました白村江戦想像図です。この想像図は私が監修したもので、『再現イラストでよみがえる日本史の現場』(朝日新聞出版、2022年)32~33頁に収められています。



■Q&A 印刷用PDFデータ(87.39KB)
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。◎第2講 令和5年5月17日(水)
「大宰府成立への道程~那津官家・筑紫大宰・筑紫総領~」
講師・回答:熊谷 公男氏(東北学院大学名誉教授)
講師・回答:熊谷 公男氏(東北学院大学名誉教授)
倭国の「任那復興」政策について
任那滅亡後、倭国の対外政策の柱が「任那復興」となった理由は何でしょうか。それはのちに新羅からの「任那の調」の貢納へと変化していきますが、倭国がこれらを執拗に求めたのは何故でしょうか。また「任那の調」とは、具体的には何でしょうか。例えば鉄資源などでしょうか。
かつて”大和朝廷による任那の植民地支配”説が事実と考えられていた時期には、その植民地であった任那が失われたのですから、倭国が「任那復興」を対外政策の柱とするのは当然のこととされていました。しかし、講座でも述べましたように、その植民地支配説が崩壊した現在では別の説明が必要です。
この倭国の「任那復興」あるいは「任那の調」貢納へのこだわり・執着について、わたくしは、5世紀前半の倭国と「任那」地域との緊密な関係にその原点があると考えています。この時期に「任那」地域からの渡来人がさまざまな先進的な文物をもたらし、当時の王権の強化や社会の技術革新をもたらしたのでした。こうしたことを通じて、「任那」地域に対する特別な思いの基礎が形づくられたのもこの時期であったと思います。列島に住まう人びとにとっても、また倭王権にとっても「任那」はかけがえのない存在であったことが、「任那復興」また「任那の調」へのこだわりに表れているものと考えています。
その「任那の調」が具体的に何をさすかは、史料が残っていないためわかりません。鉄資源とする説もありますが、わたくしはむしろ、それは倭国へのミツキとして象徴的な意味をもつものであったと考えますが、それが何であったかは不明というほかはありません。
この倭国の「任那復興」あるいは「任那の調」貢納へのこだわり・執着について、わたくしは、5世紀前半の倭国と「任那」地域との緊密な関係にその原点があると考えています。この時期に「任那」地域からの渡来人がさまざまな先進的な文物をもたらし、当時の王権の強化や社会の技術革新をもたらしたのでした。こうしたことを通じて、「任那」地域に対する特別な思いの基礎が形づくられたのもこの時期であったと思います。列島に住まう人びとにとっても、また倭王権にとっても「任那」はかけがえのない存在であったことが、「任那復興」また「任那の調」へのこだわりに表れているものと考えています。
その「任那の調」が具体的に何をさすかは、史料が残っていないためわかりません。鉄資源とする説もありますが、わたくしはむしろ、それは倭国へのミツキとして象徴的な意味をもつものであったと考えますが、それが何であったかは不明というほかはありません。



白村江敗戦後の山城築城について
山城はなぜ瀬戸内海にまで築城されているのでしょうか。また、その中の長門国の城はどこに比定できるでしょうか。
瀬戸内海にも山城が築城されたことについては、やはりヤマトまでの敵襲を想定したためであろうと思われます。また、長門国の城については、下関付近を中心にいくつかの候補地があるようですが、まだ遺跡は見つかっていません。



筑紫総領について
筑紫総領は官職名でしょうか。あるいは組織(統治機構)名でしょうか。
これについては、講座でも述べましたが、わたくしは、少なくとも『日本書紀』の白村江戦以後にみえる「筑紫大宰」については、「筑紫総領」を書き換えたものだと考えます。そのうえで、この「筑紫総領」の記事をみていきますと、『続日本紀』文武4年に石上麻呂を「筑紫総領」に任命した(講座資料レジュメ5頁)、とありますから、「筑紫総領」は官職名と考えられます。
一方で、「筑紫総領」を中核とする組織が何と呼ばれたかはよくわかりませんが、講座の中で参考文献として挙げた坂上康俊さんは、講座資料レジュメ5頁③周防の天武14年11月に「周芳総令所」がみえることから、「筑紫総領所」であった可能性を示されています。
一方で、「筑紫総領」を中核とする組織が何と呼ばれたかはよくわかりませんが、講座の中で参考文献として挙げた坂上康俊さんは、講座資料レジュメ5頁③周防の天武14年11月に「周芳総令所」がみえることから、「筑紫総領所」であった可能性を示されています。



■Q&A 印刷用PDFデータ(126.17KB)
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。◎開講式・第1講 令和5年4月19日(水)
開講式 「大宰府アカデミー開講にあたって」
講師:佐藤信氏(大宰府アカデミー・令和編 学長・東京大学名誉教授)
第1講 「大宰府の研究と調査の歩み」
講師:小田富士雄氏(大宰府アカデミー・令和編 顧問・福岡大学名誉教授)
講師:佐藤信氏(大宰府アカデミー・令和編 学長・東京大学名誉教授)
第1講 「大宰府の研究と調査の歩み」
講師:小田富士雄氏(大宰府アカデミー・令和編 顧問・福岡大学名誉教授)
開講式 「大宰府アカデミー開講にあたって」
講師:佐藤信氏(大宰府アカデミー・令和編 学長・東京大学名誉教授)




第1講 「大宰府の研究と調査の歩み」
講師:小田富士雄氏(大宰府アカデミー・令和編 顧問・福岡大学名誉教授)
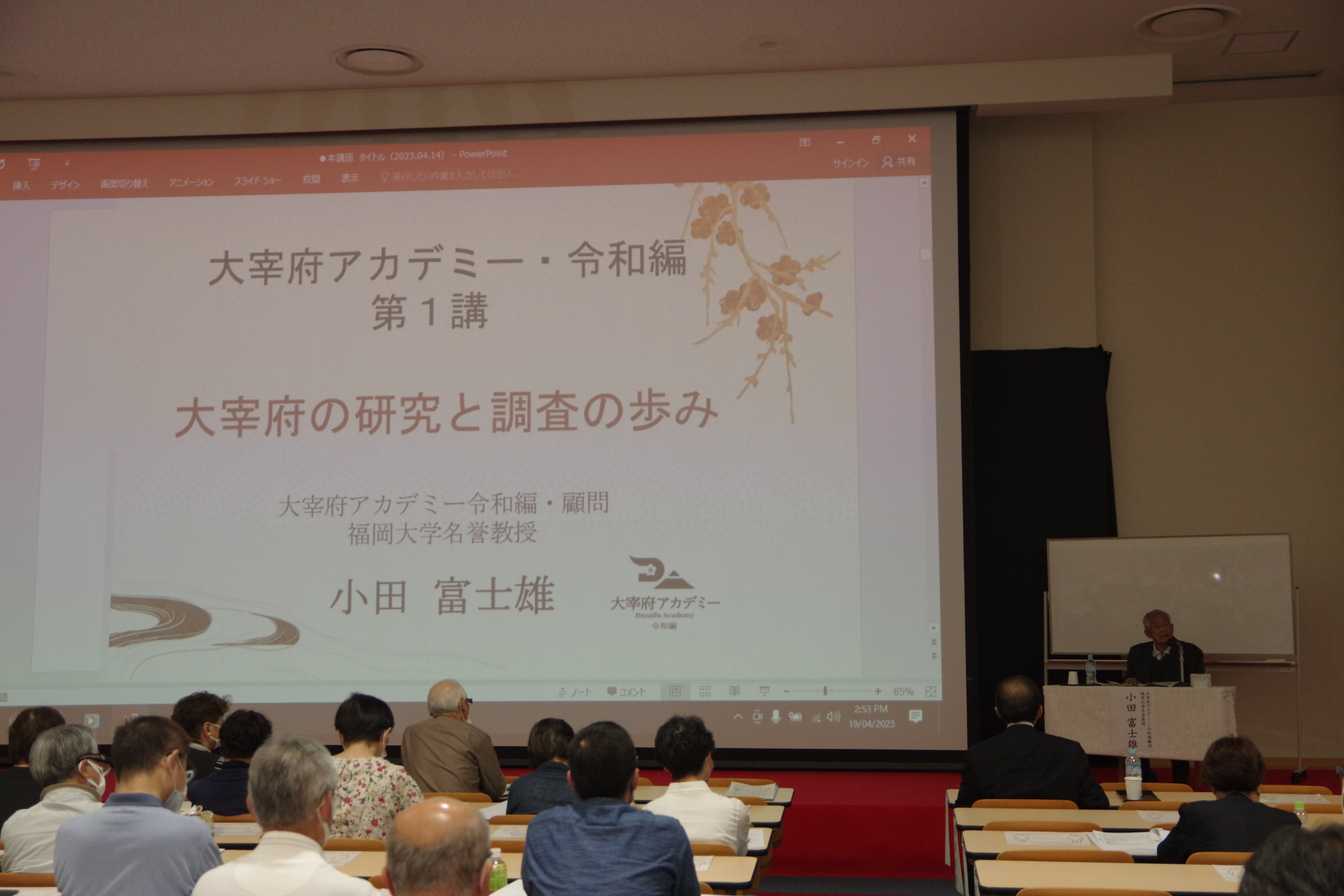



■Q&A 印刷用PDFデータ(31.56KB)
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
↑本ページで掲載している内容のPDFデータです。
印刷を希望される方は、こちらからダウンロードいただきご利用下さい。
※PDFデータをご覧いただくためにはAdobe社が提供するAdobe Reader等が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のマークをクリックいただき、リンク先から無料ダウンロードしてご覧下さい。
 ←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。
←Adobe Readerをダウンロードの際はこちらのマークをクリック下さい。